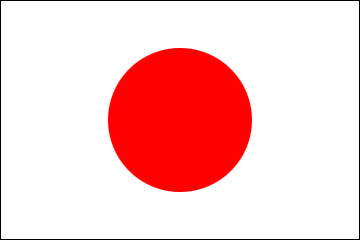戸籍・国籍関係の届出
令和8年1月14日
海外に居住する日本国籍の皆様に出生、婚姻、死亡など戸籍上の身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、日本国戸籍法又は国籍法に基づいて届出を行い戸籍に反映させることが義務づけられています。
届出は、当館または直接本邦本籍地役所へ行ってください。当館において受理している主な届出手続き等は以下のとおりです。国籍離脱届以外は、郵送でも届け出ることが出来ます。郵送で届出を提出される方は、追跡番号の付いた郵送方法を利用されることをお勧めします。郵送際の破損、紛失、遅延等につきましては、当館では一切の責任を負いかねます。提出していただいた書類は、返戻いたしませんので、各自で写しを保管してください。
その他の届出については直接当館までお問い合わせ下さい。
●戸籍に氏名のフリガナが記載されます。(2025年3月28日付 外務省ホームページ)
● 各種届出用紙の入手方法
届出用紙をご希望の方は、当館窓口で受け取られるか、又は、下記(1)~(3)を明記の上、
Forever切手3枚分 と宛名ラベルを同封して当館まで郵送してください。
当館より届出用紙一式を記載例と共に送付致します。
(1)必要な届出の種類
(2)当事者(夫妻、父母等)それぞれの国籍
(3)連絡先住所及び電話番号又はEメールアドレス
住所
Consulate-General of Japan in Nashville (Koseki)
1801 West End Avenue, Suite 900, Nashville, TN 37203
出生届
婚姻届
離婚届
死亡届
国籍喪失届
国籍離脱届
不受理申出制度
氏名の振り仮名の届
常用漢字
人名用漢字
<参考情報>
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
<日本人間の婚姻>
〈注意事項〉
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
〈注意事項〉
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
<参考情報>
法務省ホームページ「国籍離脱の届出」
法務省ホームページ「国籍を選ぼう ~重国籍の方へ~」
法務省『国籍Q&A』
【当該外国の国籍を離脱する方法】
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に外国国籍喪失届を提出してください。外国国籍の離脱手続きについては、当該外国の関係機関にご相談ください。ご参考:米市民権の離脱(国務省ウェブサイト)
【日本の国籍の選択を宣言する方法】
戸籍謄本を添付して在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出してください。
届出は、当館または直接本邦本籍地役所へ行ってください。当館において受理している主な届出手続き等は以下のとおりです。国籍離脱届以外は、郵送でも届け出ることが出来ます。郵送で届出を提出される方は、追跡番号の付いた郵送方法を利用されることをお勧めします。郵送際の破損、紛失、遅延等につきましては、当館では一切の責任を負いかねます。提出していただいた書類は、返戻いたしませんので、各自で写しを保管してください。
その他の届出については直接当館までお問い合わせ下さい。
●戸籍に氏名のフリガナが記載されます。(2025年3月28日付 外務省ホームページ)
● 各種届出用紙の入手方法
届出用紙をご希望の方は、当館窓口で受け取られるか、又は、下記(1)~(3)を明記の上、
Forever切手3枚分 と宛名ラベルを同封して当館まで郵送してください。
当館より届出用紙一式を記載例と共に送付致します。
(1)必要な届出の種類
(2)当事者(夫妻、父母等)それぞれの国籍
(3)連絡先住所及び電話番号又はEメールアドレス
住所
Consulate-General of Japan in Nashville (Koseki)
1801 West End Avenue, Suite 900, Nashville, TN 37203
出生届
婚姻届
離婚届
死亡届
国籍喪失届
国籍離脱届
不受理申出制度
氏名の振り仮名の届
出生届
日本国籍の留保
国籍取得に関して生地主義を採っている米国内で子が生まれると、その子は自動的に米国籍を取得します。子の出生時に父又は母が日本国籍を保持している場合には、出生日を含めて3ヶ月以内(例えば出生日が4月2日の場合、最終受付日は7月1日)に日本国籍留保の届(出生届の「その他」欄に署名をするもの)を伴う出生届を提出してください。この期限を過ぎると日本国籍を喪失することとなり、出生届を受け付けることは出来ませんのでご注意ください。出生届の受付日は当館窓口で受け付けた日又は郵便が当館に到着した日となります。
日本国籍を留保した場合、子は日米の重国籍となりますが、満20歳の誕生日までにどちらかの国籍を選択する手続きが必要となります。
日本国籍を留保した場合、子は日米の重国籍となりますが、満20歳の誕生日までにどちらかの国籍を選択する手続きが必要となります。
提出書類
- 出生届 2通
- 州政府発行の出生登録証明書 原本(Certified Copy)1通
又は、出産に立ち会った医師作成の出生証明書 原本1通 - 上記2.の和訳文 1通
- 日本国籍を持つ父母双方の日本のパスポート 原本提示
- 郵送で届け出る場合はコピーをお送りください。
- 日本国籍を持つ父母双方の米国での滞在資格を証する書類(米国ビザ、グリーンカード等) 原本提示
- 郵送で届け出る場合はコピーをお送りください。
- 戸籍謄本の写し(発行日が古いものでもかまいません)
- 出産した病院名、及び住所が確認できる書類
〈注意事項〉
- 出生届は届出右側の「記入の注意」をよく読んで記入し、特に「子の氏名」と「生まれたところ」は戸籍の重要な記載事項ですので、正確にご記入ください。
- 子の名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナで記入し、コンマ、中点等の記号は使用出来ません。
- 何らかの事情で届出期限(出生から3ヶ 月)以内に出生証明書が入手できない場合 は,届出期限内に当館に相談してください。
- 父母が米国の州法により結婚していても、日本の戸籍に父母の婚姻が記載されていない時は戸籍の処理が出来ませんので、父母の婚姻届を出生届と同時に提出して下さい。
- 婚姻していない日本人父と外国人母との間に生まれた子については、日本人父から胎児認知されている場合に出生と共に日本国籍を取得します。
- 郵送中の損傷、紛失につきましては当館では責任を負いかねますので、郵送にて出生届を提出される方は、トラッキング可能な郵送方法を選ぶことをお薦めします。また、届書が当館に到達したか数日後にお電話でご確認下さい。
- 日本の戸籍に記載されるには当館が受理してから1ヵ月半程度かかり、当館が各個人の戸籍の内容を確認することは出来ませんので、確認が必要な場合は直接届出人が日本の本籍地役場より戸籍謄本又は抄本を日本から取り寄せて戸籍記載の事実を確認してください。
人名用漢字一覧
常用漢字
人名用漢字
<参考情報>
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
婚姻届
提出書類
<日本人間の婚姻>
- 婚姻届 2通
- 米国官公署発行婚姻証明書(Marriage Certificate) 原本(Certified Copy)1通
- 上記2.の和訳文 1通
- 日本人当事者双方の戸籍謄(抄)本(入手が難しい方は御相談ください)
- 日本人当事者双方の日本のパスポート 原本提示
- 郵送で届け出る場合はコピーをお送りください。
- 日本人当事者双方の米国での滞在資格を証する書類(米国ビザ・グリーンカード等) 原本提示
- 郵送で届け出る場合はコピーをお送りください。
- 婚姻届 2通
- 米国官公署発行婚姻証明書(Marriage Certificate) 原本(Certified Copy)1通
- 上記2.の和訳文 1通
- 日本人当事者の戸籍謄(抄)本(入手が難しい方は御相談ください)
- 外国人配偶者の国籍を証する書類(以下のいづれか一点)
- 外国パスポート 原本提示 注1)婚姻成立時及び届出時の両方の時点で有効なもの。注2)郵送で届け出る場合は、公証人の認証を受けたコピー(Notarized Copy)を1通お送りください。
- 出生証明書 原本(Certified Copy)1通
- 上記5.の和訳文 1通
- 日本人当事者の日本のパスポート 原本提示
- 郵送で届け出る場合はコピーをお送りください。
- 日本人当事者の米国での滞在資格を証する書類(米国ビザ・グリーンカード等) 原本提示
- 郵送で届け出る場合はコピーをお送りください。
〈注意事項〉
- 日本人同士の場合、日本式に婚姻することも可能です。この場合、上記必要書類の2 及び3は不要ですが、婚姻届に成人2名が証人として署名する必要があります (州法で婚姻したときは、証人欄に記入の必要はありません)。
- 外国人との婚姻の場合、戸籍上の氏の変更はありませんが、ご希望の場合は、婚姻成立後6ヶ月以内に限り、「外国人との婚姻による氏の変更届」をすることで、戸籍上の姓(氏)をカタカナ表記で外国人配偶者の称している姓(氏)に変更することができます(届用紙は当館にあります)。それ以降は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
- 新しく本籍を設定する場合は、必ず事前に当該市区町村役場へ、希望する本籍地の設定が可能かどうか確認してください。
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
離婚届
提出書類
- 離婚届 2通
- 離婚判決謄本 原本(Certified Copy)1通
- 上記2.の和訳文 1通
- 戸籍謄本 (入手が難しい方は御相談ください)
- 日本人当事者の日本のパスポート 原本提示
- 郵送で届け出る場合はコピーをお送りください。
- 日本人当事者の米国での滞在資格を証する書類(米国ビザ・グリーンカード等) 原本提示
- 郵送で届け出る場合はコピーをお送りください。
〈注意事項〉
- 日本人同士が離婚する場合は、日本の方式で協議離婚することもできます。その場合、上記 2及び3は不要ですが、届出用紙の証人欄に成人 2 名の署名が必要です。
- 日本人同士が離婚した場合、婚姻によって氏を改めた夫又は妻は婚姻前の氏にもどります。しかし、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をすることで、離婚後も婚姻中の氏を称することができます(届出用紙は当館にあります)。
- 外国人との離婚の場合で、婚姻時「外国人との婚姻による氏の変更届」により外国人配偶者の姓に変更した方は、離婚確定日より3ヶ月以内に限り、「外国人との離婚による氏の変更届」を届けることによって、その氏を変更の際に称していた氏に変更することが出来ます(届用紙は当館にあります ) 。それ以降は、家庭 裁判所の許可を得る必要がありますのでご注意ください。
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
死亡届
米国内で邦人が亡くなられた場合、死亡届を当館に提出して下さい。
ただし、日本国内で火葬又は埋葬をされる場合は、死亡届、死亡証明書及び同和訳文を直接市区町村役場に提出してください。
提出書類
- 死亡届 2通
- 州政府発行の死亡証明書 原本(Certified Copy)1通
- 上記2.の和訳文1通
- 死亡者の日本のパスポート 原本提示
- 郵送で届け出る場合はコピーをお送りください。
- 届出人の日本のパスポート 原本提示
- 郵送で届け出る場合はコピーをお送りください。
- 届出人の米国での滞在資格を証する書類(米国ビザ・グリーンカード等) 原本提示
- 郵送で届け出る場合はコピーをお送りください。
- 在外公館で死亡届を提出すると、当該届書が本籍地の自治体に到着するまでにおおよそ 1 ヵ月半ほどかかるため、それまでに日本にて火葬又は埋葬をお考えの方は、死亡証明書(原本)と和訳文をご持参になり、日本の本籍地役場で直接死亡届を提出することをおすすめいたします。
国籍喪失届
日本国民が自己の志望により外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を喪失します。本人、 配偶者又は四親等内の親族は、国籍喪失の事実を知った日から 3 か月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。
提出書類
- 国籍喪失届 2通
- 帰化(米国市民権の取得)の事実を証明する文書
- 窓口に届け出る場合は、帰化証明書の原本を提示してください。確認後、お返しします。郵送はしないでください。
- 郵送で届け出る場合は、公証人の認証を受けた宣誓供述書(Affidavit)の原本2通を提出してください。
- 上記2.の和訳文 1通
- 日本のパスポート 原本提示
- 郵送で届け出る場合はコピーをお送りください。
国籍離脱届
日本国籍の他に外国国籍を有する場合、領事館を通して法務大臣に届け出ることにより日本国籍を離脱することができます。
この届出は、国籍離脱を希望されるご本人の意思確認の為、 ご本人(15歳未満の場合は法廷代理人)に来館していただく必要があります。郵送での受付はできません。
来館される前に、お電話にてご予約をお願い致します。
提出書類
- 国籍離脱届 2通
- 戸籍謄本 (入手が難しい方は御相談ください)
- 外国国籍を有することを証する書面(米国籍の方は以下のいずれか一方)
- 現在有効な米国パスポート 原本提示
- 出生証明書及び公証人の認証を受けた宣誓供述書 原本各1通
- 米国籍以外の場合は、事前に必要書類をお電話でご確認ください。
- 現住所を証する書面 原本提示
- 本人が15歳未満の場合は法定代理人の資格を証する書面及び身分証明書
- 上記3.~5.の和訳文
- 日本のパスポート 原本提示
<参考情報>
- 国籍の離脱は日本の法務局または地方法務局でも行うことができます。国籍の喪失・離脱について、詳しくは法務省のホームページをご参照ください。
法務省ホームページ「国籍離脱の届出」
法務省ホームページ「国籍を選ぼう ~重国籍の方へ~」
法務省『国籍Q&A』
- 日本の国籍法は、単一国籍が原則であるため、外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は重国籍になった時から2年以内に)、どちらかの国籍を選択する必要があります(国籍法14条1項)。選択しない場合は、日本の国籍を失うことがありますのでご注意ください。重国籍者による国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行ってください。
【当該外国の国籍を離脱する方法】
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に外国国籍喪失届を提出してください。外国国籍の離脱手続きについては、当該外国の関係機関にご相談ください。ご参考:米市民権の離脱(国務省ウェブサイト)
【日本の国籍の選択を宣言する方法】
戸籍謄本を添付して在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出してください。
不受理申出制度
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理できません。
日本人が不受理申出を行う場合
1.対象となる届出- 認知届、婚姻届、養子縁組届、養子離縁届
- 認知届…認知者(父)
- 婚姻届、離婚届…夫および妻
- 養子縁組届、養子離縁届…養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
- 申請人本人が窓口に直接届け出ます(郵送することは原則としてできません)。
- 不受理申出書
- 申出人の本人確認ができるもの(パスポート等の官公署が発行した顔写真入りの本人確認資料)
- 15歳未満の者について申出を行う場合は、法定代理人であることを証明する書類
- 申出書が2通必要です。また、法定代理人であることを証明する書類を提出する必要がある場合については、原本1通、写し1通が必要となります。なお、届出にあたっては、必要通数等の詳細を届出先在外公館にあらかじめご確認下さい。
- この不受理申出をしていても、外国法により成立した、または裁判により確定したことによる当該届出(報告的届出)については受理されます。
外国人が不受理申出を行う場合
日本国内であれば外国人の方も日本人を相手方とする不受理申出をすることはできますが、在外公館では、外国人の方から不受理申出を受け付けることはできません。したがいまして、外国人の方は、原則として、日本の市区町村役場の窓口に出頭して不受理申出を行う必要がありますが、自ら出頭できない事情がある場合は、書面の送付により申出できる可能性もありますので、本邦の市区町村役場にお問い合わせ下さい。